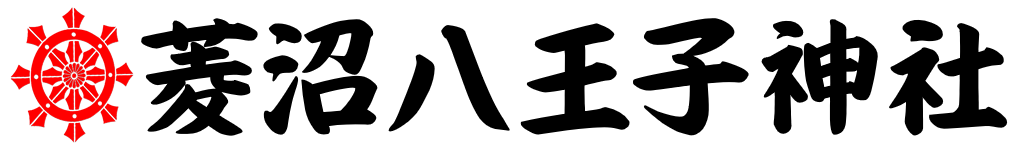1841年(天保12年)(江戸時代後期)「新編相模国風土記稿」には下記の記載が見られます。
八王子権現社 長福寺持、例祭六月十七日
「茅ヶ崎市史」には下記の記載が見られます。
1872年(明治5年)「高座郡神社氏子書帳」によりますと、下記の記載があります。
社号:八王子神社、社格:村社、神官:新田勇造、氏子:五十四戸
神仏分離の実態として別当寺の廃止と職業的神主の任命、神社由緒書き上げの資料があり、1877年(明治10年)ころをまとめた資料「第1表 市域の神社と別当寺」によりますと、菱沼八王子神社については、下記の記載があります。
神社名:八王子神社、村名:菱沼、神主:新田勇造、氏子数:54、江戸時代の別当寺:長福寺(宗派:古儀真言宗)
「第二章 社寺・小祠の民間信仰」の章には「第5表 神社一覧」の八王子神社の説明にはかきの記載があります。
祭神:天津日子根命(あまつひこねのみこと)
祭礼:7月25日
二十四日が宵宮で芝居をした。翌日は神楽をした。
幟立てなどお祭りの準備は町内で交代にした。
祭りにはお囃があり。昔はお宮で叩いているだけであったが、後に車に飾りつけをし、太鼓を乗せて歩くようになった。
二十五日の朝は暗いうちに神輿が出る。
提燈を持ち、当番の家が赤飯のムスビをつくり、ヒツに入れ、神輿と一緒に浜まで行った。浜に行ってムスビを食べる。
当番の家というのは世話人の中のギョウジという役の人。
浜に神輿が行ったのは昭和十年ぐらいまでで、その後は祭りのとき神輿を外に出して飾るだけになった。
神輿が浜へいってくると、そのあと部落中を回った。
七月十五日の浜降り(神幸祭といっている)にも古くから参加していた。
神奈川県神社誌(1981年:昭和56年)によりますと
明治前期
菱沼村
戸数70(寺1,社2)
人口374(男185,女189)
小字・町名 吹切,津戸田,後田,手城塚,前ノ田,木ノ下,網久保,流し面,九丁九反歩,身持田
神社(祭礼日) 八王子神社(8/17),稲荷社
寺院 長福寺(真言宗)
菱沼八王子神社

八王子神社の創立は不詳ですが1705年(宝永2年12月(江戸時代中期、元禄に続く時代)に再建され、1928年(昭和3年7月25日)に再度再建されました。
本殿は神明造り、拝殿は権現造で建築されています。