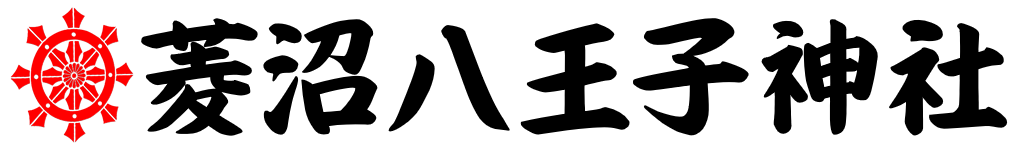「菱沼」の詳しい歴史です。
1326年(嘉暦元年11月7日)(鎌倉時代後期)の「左大弁清閑寺資房奉書」には「相模国大庭御厨内菱沼郷」の記載が見られます。
1519年(永正16年4月28日)(安土・ 桃山時代)の「宗瑞(伊勢長氏)箱根領注文」には菊寿丸知行分として「百廿くわん文 ひしぬま」との記載が見られます。
1841年(天保12年)(江戸時代後期)の「新編相模国風土記稿」には菱沼村と小和田村について下記の記述が見られます。長いですがそのまま引用します。
菱沼村(比之奴末牟良)
江戸より行程十三里、此地小和田村と地形錯雑する。故に四隣広袤[ボウ]等は彼村に括載す、且古地頭の沿革も亦同じ、正保の改に村名を載せず、さては其頃小和田村に併入せしと知らる。
地名旧くは北条早雲永正十六箱根別当金剛王院への寄附状に見ゆ。
「北条役帳」にも見えたり。戸数五十四、今御料所なり。
東海道村の中程を貫く。
高札場
小名 網久保,長元,神田,高砂,東出口,出口,蔵ノ山
八王子権現社 長福寺持、例祭六月十七日
長福寺 菱沼山薬師院と号す、古義真言宗、本尊薬師を安ず中興快祐と伝ふ。
鐘楼宝暦十二年の鋳鐘をかく。
釈迦堂 長福寺持。
小和田村(古和太牟良)
江戸より行程十三里、地形菱沼村と犬牙して分ち難し、故に此に合載す。広十五町袤[ボウ]十二町余(東、辻堂村、西、室田・茅ヶ崎二村、北、赤羽根村南は海)戸数百十、今御料所にして(宝暦十二年御料所となる。
村内上正寺縁起に拠ば、もとは大久保七郎右衛門忠世、杉浦越後守正友知行なりしと云う)。
安永元年江川太郎左衛門英征検地せし新田あり、東海道(幅六間)村内を貫く、
中間に小流あり、橋を泪橋と唱ふ、(鎌倉時代茅崎村に刑場ありしよりの遺命なりと云ふ)又大山道(幅一間半)係れり、当村にも海浜に砲術場あり。
高札場
小名 牡丹餅(海道立場を云ふ)、浜竹
御林五所
熊野社 村の鎮守なり、千手・広徳二寺の持、下同じ
尾根明神社 祭神詳ならず
牛頭天王社
山王社
広徳寺 山王山観音院と号す、古義真言宗(藤沢感応院末)本尊千手観音を安ず、
開山を慶海(寛永九年二月廿四日寂す)と云ふ。
千手院 天王山神保寺と号す(本寺前に同じ)本尊千手観音を置。
開山元栄(元和八年六月十一日寂す)と云ふ。
稲荷社
閻魔堂
上正寺 龍澤山龍徳院と号す、浄土真宗(京東六条本願寺末)本尊阿弥陀(恵心の作)
元禄十五年僧円春が記せし境内太子堂縁起に拠に。円融院第四皇子尊勝法親王
(按するに皇胤紹運録に親王の名諱所所見なし、全く縁起の杜撰と云ふへし)
郡中寺尾郷に一宇を建て、海円院と号し、顕密兼学の霊場とす。文治年中
当村に移る(頼朝巳来北条足利代々の朱印判物等有しか今紛失す)其後嘉禄中、
住僧了智、親鸞に国府津に謁し其宗法を帰依し今の宗派に改む。因って了智を
宗の開基とす。其頃親鸞寺号を無上正覚寺と名つく。後寺務を智円に譲り
信州松本に正行寺を建て。仁治二年二月二十九日其他にて寂す。斯て後
本山覚如巡国の時当寺に経過し寺号を略して上正寺と呼しより今の唱と
なれりと云ふ。壇杉浦越後守正友、法諡を龍徳院と号す。今の院号は是に
因ると云ふ。(境内に正友の碑あり)
寺宝
十字名号一幅(祖師真筆開基了智に授与の物と云ふ下同じ)
六字名号一幅
草稿正教一幅
六字名号一幅(宣如筆)
和歌六首一幅(円意筆)
鐘楼天明三年十月再鋳の鐘を掛く。
太子堂 太子自刻の像を安す(縁起略曰太子巡国の砌[ミギリ]広野に駒をとどめ
真影を彫刻し当国に残し給ふ、然[シカル]に尊勝法親王関東遊化の時、此墓告
により立入て尊像を拝し帰洛ありて帝に奏して一宇を創造すと云ふ)側に
十字名号を掛く。
塔頭 無覚坊 宝暦中廃す
阿弥陀堂 千手院持
1889年(明治22年3月31日)の神奈川県令第9号「町村分合改稱」別冊によると
1889年(明治22年4月1日)に町村制施行により、室田村、高田村、赤羽根村、甘沼村、香川村、小和田村および菱沼村が合併し松林村となっています。
1908年(明治41年10月1日)に、高座郡松林村と茅ヶ崎村および鶴嶺村と合併し茅ヶ崎町となっています。
1924年(大正13年)以降の小和田菱沼地区人口推移を下記に示します。